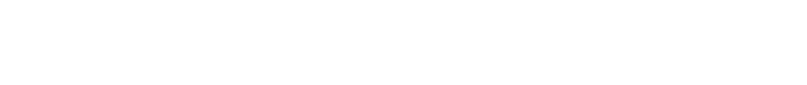投稿日 2025/08/07
まずはこの動画を見て欲しいのですが、MTBのリアサスペンション方式の一種であるハイピヴォットの特徴をよく捉えています。便宜上、ロワーマウントからリアショックを外して撮影していますが、アイドラープーリーにチェーンを通した時と、通さない時の違いが明確に分かります。
アイドラープーリーが無い場合はクランクが戻ってきていますが、具体的にこれを走行中に再現すると、例えば深いバームを曲がってサスペンションが沈み、コーナーの出口ではサスペンションが圧縮された状態から戻るので、コーナーの立ち上がりでクランクが逆回転してくることになります。
このクランクが戻ってくる現象はキックバックと呼ばれ、いわゆるサスペンションの「おつり」です。サスペンションの動きを阻害したり、チェーンテンションが失われたりで百害あって一利なしの現象なのですが、ライダーによってはこのキックバックでクランクが戻ってくる瞬間にガンっと踏んで、コーナーで加速できるような感覚を得ることができるので、キックバック量によっては好まれる場合もありましたが、理論上ではほぼメリットはありません。
フルサスペンションのMTBは1990年代前半辺りから盛んに開発が続けられてきましたが、本当の意味でバイクデザイナーの目を覚ませたのはこのアーロン・グインによる2015年のWCでの有名なランでした。スタートゲートを越えてペダルを踏んだ瞬間にチェーンがスナップして、そのままチェーンレスで走って優勝してしまったのです。レオガンというコースの特性や、グイン自身がライダーとして絶頂期だったせいもありますが、これを見てMTB業界全体が「もしかしてチェーンは害悪なのでは?」と気づいてしまったのです。
ここからダウンヒル機材は怒涛の勢いで革新が進み、まずホイール径が26"から前後27.5"、そして前後29er、現在では前が29erでリアが27.5"のマレットに落ち着いています。車両のホイール径がここまで短期間に変わったというのはロードバイク畑の人には意味がわからないくらいの進化だと思います。ジオメトリーもいわゆるロング&スラックと言われるロングホイールベースかつ寝たヘッドアングルへと変わりました。そして総仕上げがハイピヴォット+アイドラープーリーです。
「チェーンは害悪」という話が出ましたが、実は2015年までのMTB業界はチェーンを友達だと思っていましたし、今でもある程度は友達です。というのは、サスペンションの使い方を効率よくするため、チェーンを積極的に利用していたのです。MTBに乗ると、リアのサスペンションがペダリングの動きに合わせて上下にヒョコヒョコと動きますが、これをペダルボブや単純にボブ、ボビングなどと言います。当然、ボブが発生することによりパワーの損失が発生しているので、なるべくボブの少ないサスペンションのレイアウトを各社が考えて導入してきました。これをアンチボブといいます。
具体的には、ペダルを踏んでチェーンリングでトルクが発生すると、逆に後輪が地面に押し付けられる、つまりリアスペンションが伸びる方向に作用する、これがアンチボブです。アンチボブは数字で表すことができるのですが、ペダル入力でリアサスペンションが沈まない、ペダリングの力と拮抗した状態はアンチスクワット率が100%だと表現します。これが100%より下の数値ならサスペンションが沈む方向、上の数字なら伸びる方向に働きます。
例えば、スペシャライズドのEPICはサグの状態でアンチスクワット率が100%だそうです。EPICはXC用レースバイクなので、極めてペダル効率が高い味付けがされているのです。ちなみに、サグとは人間がバイクにまたがった場合にサスペンションが沈む量で、EPICなら全トラベル量の25-30%が推奨されています。
ここからが面白いのですが、アンチスクワットはリアサスペンションのストロークによって変化します。この変化はアンチスクワット曲線で説明されます。一般的に、XC系のバイクはトラベルの後半でもアンチスクワット率はそれほど下がらず、DH/ENDUROバイクならサグ付近では100%で、トラベル後半でスクワット率は急速に低くなるよう設計がされています。これはリアサスペンションが沈んだ状態でペダリングするようなことはあまり無いので、サスペンションの動きを優先しているからです。
結果的にアンチスクワット特性の設計がシングルピヴォットのバイクに比べて自由度が高いため、DW-LINK、ホルストリンク、マエストロなど呼び名は色々とありますが、根本的には同じサスペンションシステムがマーケットを席巻してきました。しかし、最近のトレンドとしては、XC系の軽量なバイクはキャノンデールお得意のピヴォットレスのスイングアームを採用した、いわゆるカーボンの「しなり」を活かしたシングルピヴォットのバイクが主流になってきました。TREKのスーパーキャリバー、スペシャライズドのEPIC、CANYONのLUXあたりは全て同一のサスペンション方式です。
しかし、200mm前後のトラベル量を誇るDHバイクではシングルピヴォットで質の高いサスペンショントラベルを生み出すのが難しいので、複雑なリンクを持つものが多かったのですが、最近はTREK SLASHのようなシングルピヴォットで170mmトラベルを持つバイクも出てきました。やっと本題に入りますが、それはアイドラープーリーを追加したハイピヴォットだからです。
この動画がとても良くできているので見て欲しいですが、ギアボックス+ハイピヴォット+アイドラープーリーの利点を分かりやすく説明してくれています。ギアボックスをBB付近に搭載してRDをリアエンドから排除してマスの集中化を実現、ハイピヴォットにより後輪の軌跡を最適化してサスペンションの動きを理想的なものに、アイドラープーリーによりペダリングがサスペンションに与える悪影響を排除しています。

アイドラープーリーの役割はペダリングとサスペンションを切り離すことで、メインピボットになるべく近い位置にプーリーを配置することにより効果を最大にします。上の画像はTREK SLASHですが、アイドラープーリー上部のチェーンが掛かっている位置のすぐそばにメインピヴォットがあるので、ペダリングによるボビングを最小限にしています。
という訳で、ハイピヴォット+アイドラープーリーが理想的なのかと言うと、確かに理想に近いのですが、ネガティブな点もあります。まず、チェーンが長くなります。つまり、重くなり、抵抗も増えます。アイドラープーリーが追加されたことにより、ここでも抵抗が発生します。しかもアイドラープーリーのサイズが小さい場合は抵抗がさらに大きくなるので、大きな歯数のものを入れる場合が多く、しかも摩耗が早いのでステンレスや鉄を採用するとさらに重くなります。それでもここまでハイピヴォットが増えたのは、それほどペダリングを必要とせず、軽量化が重視されないDHI競技ゆえです。
 こちらは今季WCで破竹の4連勝を遂げて話題のジャクソン・ゴールドストーンのサンタクルーズV10ですが、なんとダウンチューブの下にベルクロで1.8kgのリードウェイトが追加しています。わざわざバイクを重くするのは理由があり、まずジャクソンは体重64kgとWCサーキットも最も軽量級のため、バイクを重くして安定性を増すためです。また、メインフレームを重くすることによりバネ上/バネ下の重量比を上げることによりリアサスペンションがより敏感に動くようになります。
こちらは今季WCで破竹の4連勝を遂げて話題のジャクソン・ゴールドストーンのサンタクルーズV10ですが、なんとダウンチューブの下にベルクロで1.8kgのリードウェイトが追加しています。わざわざバイクを重くするのは理由があり、まずジャクソンは体重64kgとWCサーキットも最も軽量級のため、バイクを重くして安定性を増すためです。また、メインフレームを重くすることによりバネ上/バネ下の重量比を上げることによりリアサスペンションがより敏感に動くようになります。
僕自身もTREKのE-MTBに乗っていますが、メインフレームに重いバッテリーが内蔵されているため、非常に高いバネ上/バネ下の重量比を実現しているため、ダウンヒルでの安定性が驚くほど高いのです。たまにペダルバイクに乗ると不安になるほどです。それくらい、下りで戦うダウンヒル競技では単純な軽量性は求められていません。

そして極めつけがこれです。クランクに装着されたOchainというデバイスです。
この動画を見て欲しいのですが、キックバックをチェーンリングでキャンセルするものです。2020年の世界選手権でリース・ウィルソンがこれを採用して世界王者に輝いているのですが、僕もその時はノーマークでした。しかし、ここから1年もすると、こぞってトップライダー達が自費で購入して使うようになったのです。
すると、つい先日にSRAMがOchainを買収してしまったのです。イタリアで一人のおじさんがガレージで創業したブランドをSRAMが買収するという夢のようなストーリーなのですが、これによりますますOchainへの信憑性が増しました。
しかし、V10のフレームデザイナーの立場なら、自分が理想的な設計をしたはずのフレームにOchainとウェイトまで追加されてしまい、複雑な心境のはずです。

そしてもう一つOchainの効果を裏打ちしているのが、アメリカが久しぶりに生み出したした天才、エイサ・ヴァーメットの乗るFrameworks Bicyclesです。レジェンドライダーのネコ・ミュラリーがレジェンド・フレームビルダーのFTWと組んで生み出したフレームですが、僕自身は正直戦闘力は低く、WCでは勝負にならないとさえ思っていました。しかし、エイサは今季安定してポディウムに乗っているし、Red Bull Hardlineではジャクソン・ゴールドストーンを抑えて優勝(追記: 大島礼治から指摘があり出てないそうです)、全米選手権も連覇しています。
もちろん、MTB DHIというのはモータースポーツとは違って、乗り手の技量が決定的なので、乗り手が優秀なら何に乗ってもある程度は速いのですが、このFWのフレームのように、複雑なリンケージを持たないサスペンションシステムでもOchainがあればWCで戦えるのでは?思ってしまいます。なんせ、このフレームは20年前の名車、TURNER After Burner DHとなんら変わらない構成をしているのです。
という訳で、現在はOchainを採用したシンプルなシングルピヴォットのバイクと、コメンサルのSupreme DHのような複雑なリンクとハイピヴォット+アイドラープーリーを組み合わせたバイクが互角に戦っている状況で、非常に面白いです。個人的にF1を熱心に見ているのですが、コンストラクターが変わるとあのルイス・ハミルトンでさえ簡単には適応できないし、あれだけ勝利を重ねたメルセデスやRed Bullでさえもクルマが遅くなるとドライバーは勝てなくなるし、とにかくクルマの占める割合が極めて大きいのです。
しかし、MTBのDHIは機材の予算に上限がなく開発もやりたい放題、空力に関する規制もないし、開発の自由度が高いのが良いです。しかも、ガレージメーカーのようなFWでもスペシャライズドのような潤沢な予算のあるチームと真っ向勝負して勝つことさえあるのです。イタリアのおじさんがガレージで生み出したプロダクトがSRAMに買われるなんて夢があると思いませんか。F1では絶対にありえません。
そしてこれは蛇足かもしれませんが、ロードレースを見ていて常に付きまとう不安で「推しの選手はドーピングしていないだろうか?」というのがありますが、ダウンヒルに関してはドーピングしても重要な能力は鍛えることができません。実際、過去に発覚したドーピングはTHCくらいなのです。
観戦型スポーツとしてのダウンヒルは超おすすめです。今一番おもしろいかもしれません。機材のトレンドが今後どのように進むのかも注目です。
毎週金曜日発行 メルマガの登録はこちらから